古文訳
夜に浮かんでいた海月のような月が爆ぜた。
夜に浮かべる海月のごとき月爆ぜき。
バス停の背を覗けば、あの夏の君が頭にいるだけ。
乗合停の背を覗かば、かの夏の君が頭なるばかり。
鳥居 乾いた雲、夏の匂いが頬を撫でる。
鳥居 乾きし雲、夏の匂ひが頬を撫づ。
大人になるまで、ほら、背伸びしたままで。
おとなしくなるまでは、背伸びせるままに
遊び疲れたらバス停裏で空でも見よう
遊びこうぜば乗合停裏に空にも見む
じきに夏が暮れても、きっときっと覚えてるから。
じきに夏暮るとも、さだめてさだめて覚えたれば。
追いつけないまま大人になって、君のポケットに夜が咲く。
追ひつけぬままおとなしくなりて、君の隠しに夜咲く。
口に出せないなら僕は一人だ。それでいいからもう諦めてるだけ。
口にえいださざらば我は一人なり。それにてありぬべければいま思ひ絶えたるばかり。
夏日、乾いた雲、山桜桃梅、錆びた標識。
夏日、乾きし雲、山桜桃梅、錆びし標識。
記憶の中はいつも夏の匂いがする。
思ひ出の中は日ごろ夏の匂ひす。
写真なんて紙切れだ、思い出なんてただの塵だ。
影など紙切れなり、思ひ出などただの塵なり。
それがわからないから、口を噤んだまま。
それわからねば、口を噤みしまま。
絶えず君のいこふ、記憶に夏野の石一つ。
絶えず君のいこふ、思ひ出に夏野の石一つ。
俯いたまま大人になって、追いつけない。
俯きしままおとなしくなりて、追ひつけず。
ただ君に晴れ。口に出せないまま坂を上った。
ただ君に晴れ。口にえいださぬまま坂を上りき。
僕らの影に夜が咲いていく。
我らの影に夜咲きゆく
俯いたまま大人になった君が思うまま手を叩け。
俯きしままおとなしくなりき
君の思ふまま手を叩け
陽の落ちる坂道を上って
陽の落つる坂道を上りて
僕らの影は
我らの影は
追いつけないまま大人になって
追ひつけぬままおとなしくなりて
君のポケットに夜が咲く
君の隠しに夜咲く
口に出せなくても僕ら一つだ
口にえいださずとも我ら一つなり
それでいいだろ、もう
それにてありぬべからむ、いま
君の想い出を噛み締めてるだけ
君の想ひいで噛み締めたるばかり
助動詞「き」
この歌詞には、古文でよく用いられる文法が多数含まれています。
「き」は、古典的な日本語における助動詞の一つです。動詞の未然形に接続して、「~しまう」という意味を表します。また、連用形に接続して、動作や状態が継続している状況を表すこともあります。
例えば、「俯きしままおとなしくなりき」という句は、「俯きしままおとなしくなってしまいき」と解釈されます。この場合、「~してしまう」という意味で、「俯きしまま」つまり「うつむいたまま」で、「おとなしくなってしまい」、さらに「き」という助動詞がついて、「そのままおとなしくなっていた」という意味になります。
また、「き」は、現代語においても、方言や古風な表現として使用されることがあります。「食べきっきれない」「見ていきましょう」「考えきれない」などのように、「~きれない」や「~きましょう」という形で使用されることがあります。
副助詞「ばかり」
「ばかり」は、古文では、現代語の「だけ」「ばかりか」「だけでなく」などと同様に、限定や強調の意味で用いられていました。また、「ばかり」が句読点のように使われ、前後の文脈によって意味が変わることもあります。例えば、以下のような使い方があります。
「山は青く、空は白きばかりか、道は険しく、人はなかりけり。」 →「ばかりか」は、前半の内容を強調する助詞として用いられています。
「心を遣うる人は、口ばかりより行いを成すべし。」 →「ばかり」は、「だけでなく」という意味で用いられています。
以上のように、この歌詞は古文の特徴的な文法が多用された文体となっています。
絶えず人いこふ夏野の石一つ(正岡子規)
「絶えず人が行きかう夏野の石一つ」
この句は、夏の野原にある一つの石を詠んでいます。夏野には多くの人が行き交う場所であり、その中で一つの石が存在していることが強調されています。この句は、単純な風景描写のように見えますが、その中に「変わりゆく世界の中でも永遠のものがある」という作者の思いが込められているとされています。また、季節感や自然の美しさを表現した句でもあります。
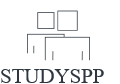



コメント