こんにちは!小学3年生の作文の書き方について、わかりやすくご紹介します。作文は自分の考えや経験を伝える大切な力を育てます。このガイドを読めば、お子さんも作文が楽しくなるはずです。
作文の書き出しテクニック完全ガイド:読者を引き込む導入文の書き方
作文の基本:「はじめ・なか・おわり」を意識しよう
はじめ(導入部分)
役割: 読み手に「何について書くか」を伝える大切な部分です。
- 書く内容の全体像を簡潔に示します
- 5W1H(いつ・どこで・だれが・なにを・なぜ・どのように)を意識して書きましょう
文章量: 全体の約2割程度(例:400字の作文なら80字程度)
書くべきこと:
- いつ、どこで、だれと、何をしたのかを明確に
- 作文のテーマや題材の紹介
- 読み手の興味を引く一文から始めるとよい
例文: 「先週の日曜日、家族で近くの公園に桜を見に行きました。」 「運動会の日は、朝から晴れていて、とても暑い一日でした。」 「夏休みに、初めておじいちゃんの家で一人でお留守番をしました。」
なか(展開部分)
役割: 作文の中心となる部分で、出来事や体験を詳しく伝えます。
- 時間の順序に沿って書くと分かりやすい
- 具体的なエピソードや詳細を書く
文章量: 全体の約6割程度(例:400字の作文なら240字程度)
書くべきこと:
- 何があったのか、具体的な出来事
- 見たもの、聞いたこと、感じたことを五感を使って表現
- 「まず」「次に」「そして」「それから」などの言葉を使って順序立てる
- 自分の気持ちの変化も書く
例文: 「公園に着くと、大きな桜の木がたくさん咲いていました。ピンク色の花びらが風に舞って、まるで雪が降っているようでした。弟は花びらを集めて喜んでいました。私は木の下でお弁当を食べました。お母さんの作ったおにぎりは、桜の下で食べるととても美味しく感じました。」
おわり(結論部分)
役割: 作文のまとめとして、感想や学んだこと、これからの希望などを書きます。
- 体験から得たことや感じたことを伝える
- 未来への思いや決意を書くこともある
文章量: 全体の約2割程度(例:400字の作文なら80字程度)
書くべきこと:
- 体験を通して感じたこと、考えたこと
- 心に残ったこと、印象に残ったこと
- これからしたいこと、次の目標
- 「〜でした」「〜と思いました」などの過去形で締めくくる
例文: 「桜の花を見て、春がきたなあと感じました。また来年も家族みんなで見に来たいです。」 「初めてのお留守番は少し怖かったけれど、自分でできることが増えて嬉しかったです。次は料理にも挑戦したいと思います。」
「はじめ・なか・おわり」を使った小さな作文例
題名:「はじめてのクッキー作り」
はじめ: 先週の土曜日、お母さんと一緒に初めてチョコチップクッキーを作りました。
なか: まず、バターと砂糖を混ぜました。泡立て器を使うのは難しかったけど、お母さんが手伝ってくれました。次に、卵と小麦粉を入れてこねました。生地がべたべたして手にくっついて大変でした。そして、チョコチップを入れて丸く形を整えました。オーブンで焼いている間は、いい匂いがして待ち遠しかったです。できあがったクッキーは、端っこが少し焦げていました。
おわり: 自分で作ったクッキーは少し形が悪かったけれど、とても美味しかったです。次は一人でも上手に作れるようになりたいです。
作文を書く前の準備
- メモを取る: 書きたいことを「はじめ・なか・おわり」に分けてメモしましょう
- 構成表を作る: 紙を三つに分けて、各部分に書くことをまとめる
- 時系列を整理する: 「なか」の部分は特に、出来事の順番を整理しておく
この「はじめ・なか・おわり」の構成を意識して書くことで、読みやすく、内容が伝わりやすい作文が書けるようになります。まずはこの基本形を身につけ、少しずつ自分らしい表現を加えていきましょう。
作文が楽しくなる5つのポイント
1. 五感を使って書こう
五感(見る・聞く・触る・嗅ぐ・味わう)を使った表現を取り入れると、読む人が情景を想像しやすくなります。
見る(視覚)の例:
- 「空は真っ青で、雲一つありませんでした」
- 「桜の花びらが風に舞って、ピンクの雪みたいでした」
- 「校庭いっぱいに並んだみんなの笑顔が、太陽のように明るく見えました」
聞く(聴覚)の例:
- 「運動場からは、元気な声援とピーッという笛の音が聞こえてきました」
- 「雨の音がトントンと屋根を叩いていました」
- 「祭りの太鼓の音がドンドンと胸に響きました」
触る(触覚)の例:
- 「砂浜の砂は、足の指の間にサラサラと入ってきました」
- 「風が頬をなでて、気持ちよかったです」
- 「おばあちゃんの手は、少ししわがあるけど温かくて柔らかでした」
嗅ぐ(嗅覚)の例:
- 「給食室からカレーの香ばしい匂いがしてきました」
- 「雨上がりの公園は、土のにおいがしました」
- 「焼きたてのパンのいい匂いで、お腹がぐーっと鳴りました」
味わう(味覚)の例:
- 「スイカは甘くて冷たくて、夏の味がしました」
- 「おばあちゃんの作ったみそ汁は、少し塩辛かったけど、なぜかほっとする味でした」
- 「初めて食べた梅干しは、すっぱくて顔がしかめっ面になりました」
2. 具体的に書こう
「楽しかった」「おもしろかった」だけでなく、どのように楽しかったのか、なぜおもしろかったのかを具体的に書きましょう。
具体的でない例と具体的な例の比較:
具体的でない: 「遠足は楽しかったです。」
具体的: 「遠足では、友だちと山道を登りながら虫を見つけたり、頂上でお弁当を食べたりして、一日中笑顔でいられて楽しかったです。」
具体的でない: 「給食がおいしかったです。」
具体的: 「給食のカレーライスは、ジャガイモがほくほくしていて、ルーがちょうどいい辛さで、おかわりをしたくなるほどおいしかったです。」
具体的でない: 「友だちと遊んで面白かったです。」
具体的: 「友だちと鬼ごっこをしたとき、鬼の太郎くんがこっそり木の陰から出てきて、びっくりして大笑いになって面白かったです。」
3. 自分の気持ちを書こう
出来事だけでなく、その時感じた気持ちや考えを書くと、読む人の心に届く作文になります。
気持ちの表現例:
- 「初めてのリレーで、バトンを落としそうになった時は、ドキドキして手が震えました」
- 「弟が私の作った折り紙を大事そうに持っているのを見て、教えてあげて良かったなと思いました」
- 「初めて自分で植えた種から芽が出た時は、まるで宝物を見つけたようにうれしかったです」
- 「友だちにケンカして仲直りできた時は、胸のつかえがとれたようにほっとしました」
- 「テストで間違えた問題を見直したとき、くやしくて泣きそうになりましたが、次は頑張ろうと思いました」
気持ちの変化を表現する例: 「はじめは怖かった校外学習のスケート教室。手すりにつかまって少しずつ滑っていると、だんだん楽しくなってきました。転んでも痛くないことがわかると、もっと速く滑りたいという気持ちになりました。」
4. 順序を考えて書こう
出来事を時間の順番に沿って書くと、読みやすい作文になります。時を表す言葉を使うと、流れがわかりやすくなります。
時を表す言葉の例:
- まず、最初に、はじめに
- 次に、それから、その後
- しばらくして、少したつと
- 最後に、ついに、とうとう
- 〜時間後、〜日後
順序を示した作文例: 「まず、朝早く起きて、お弁当を準備しました。次に、リュックサックに水筒と帽子を入れました。それから、友だちと待ち合わせた公園に行きました。少したつと、みんなが集まってきて、先生の話を聞きました。そして、バスに乗って動物園に向かいました。最後に、みんなで記念写真を撮って帰りました。」
5. 絵や図を添えてみよう
作文に絵や図を添えると、言葉だけでは伝えにくいことも表現できます。また、作文を書く前に絵を描くことで、頭の中が整理されることもあります。
絵や図を活用するコツ:
- 作文を書く前に簡単な絵を描く:
- 行った場所の様子
- 印象に残った物
- 体験した出来事の流れ
- 作文の中で説明しにくい部分を図解する:
- 複雑な遊びのルール
- 工作の作り方
- 場所の位置関係
- 絵と文章を組み合わせた作品づくり:
- 絵日記形式で書く
- マンガのコマ割りで表現する
- 地図に説明文を加える
実践例: 「運動会のリレーで走ったコースの図」を描いて、「ここでバトンを受け取りました」「この曲がり角で転びそうになりました」など、具体的な場所と出来事を関連付けて説明できます。
「観察した植物の成長記録」として、日ごとの変化を絵で表しながら、気づいたことや感じたことを書き添えると、より分かりやすくなります。
これらの5つのポイントを意識して作文を書くと、自分の体験や気持ちをより生き生きと表現できるようになります。最初は1つのポイントから試してみて、少しずつ取り入れていくと良いでしょう。作文が楽しくなるだけでなく、読む人も楽しめる文章になりますよ。
作文の題材の選び方
1. 日常の出来事から選ぶ
- 身近な体験は、自分の言葉で表現しやすく、気持ちも書きやすい題材です。
- 学校の行事や思い出
- 遠足・校外学習: 行った場所で見たもの、友だちとの会話、楽しかったこと
- 運動会: 練習の様子、本番での緊張感、競技中の出来事、応援の様子
- 音楽会・学習発表会: 練習で大変だったこと、本番での成功体験や失敗談
- 給食の思い出: 好きなメニュー、給食当番の体験、友だちとの会話
- 図書室での発見: 見つけた面白い本、図書委員の体験
- 家族との思い出
- 家族旅行: 初めて行った場所、見た景色、家族との会話
- お買い物: スーパーでの出来事、欲しかったものを買ってもらった体験
- おでかけ: 公園、映画館、動物園、水族館などでの体験
- 家族の行事: 誕生日会、季節の行事(お正月、クリスマスなど)
- 家での出来事: 停電があった日、家の模様替え、ペットとの思い出
- お手伝いの経験
- 初めてのお手伝い: 料理、洗濯、掃除などの体験
- 家族の役に立った体験: 喜んでもらえたこと、感謝されたこと
- 失敗したけど学んだこと: うまくいかなかったお手伝いとその後の成功
- 友だちとの体験
- 一緒に遊んだ思い出: 公園や友だちの家での遊び
- 仲直りした体験: けんかして仲直りした経緯や気持ち
- 協力した体験: グループ活動、班活動での協力体験
- 友だちから教わったこと: 新しい遊び、考え方など
2. 好きなことや得意なことについて書く
- 自分の興味や関心事は、詳しく書きやすく、熱意が伝わる題材になります。
- 趣味や習い事
- スポーツ: サッカー、水泳、体操などの練習や試合の様子
- 音楽: ピアノやバイオリンの発表会、好きな曲
- 絵画・工作: 作品を作った過程、完成したときの気持ち
- ゲーム: 好きなゲームのルールや面白いところ(適切な範囲で)
- コレクション: 集めているもの(切手、石、カードなど)の紹介
- 好きな本・映画・アニメ
- 心に残った本: あらすじ、好きなキャラクター、感想
- 面白かった映画: 内容、印象に残ったシーン、観た後の気持ち
- 好きなアニメ: キャラクターの紹介、好きな理由
- 自分で作った物語: オリジナルの短い物語や続き話
- 将来の夢
- なりたい職業: 医者、教師、パン屋さんなど、その理由
- やってみたいこと: 行ってみたい場所、挑戦してみたいこと
- 憧れの人: 尊敬する人物とその理由
- 好きな食べ物
- お気に入りの給食メニュー: 好きな理由、思い出
- 家族の料理: お母さんやお父さんの得意料理、特別な日の料理
- 自分で作った料理: 作り方、味、家族の反応
- 初めて食べたもの: 新しく挑戦した食べ物の味や感想
3. 季節の行事や自然について書く
- 季節感のある題材は、五感を使った表現が豊かになります。
- 春の題材
- 桜: 花見の様子、散る桜の美しさ
- 新学期: 新しいクラス、担任の先生、友だちとの出会い
- 春の遠足: 行った場所、見つけた春の花や虫
- こどもの日: 鯉のぼり、柏餅、家族での過ごし方
- 夏の題材
- 夏休みの思い出: 海水浴、山登り、昆虫採集
- プール: 水泳の上達、友だちとの水遊び
- 花火大会: 見た花火の色や音、感動したこと
- 夏祭り: 屋台、盆踊り、神輿など
- 自由研究: 取り組んだテーマ、工夫したこと、発見
- 秋の題材
- 運動会: 競技の様子、応援、練習の成果
- 秋の遠足: 紅葉狩り、落ち葉拾い
- お月見: 見た月の様子、家族との団らん
- 収穫: 稲刈り体験、芋掘り、果物狩り
- 冬の題材
- 冬休みの思い出: お正月、クリスマス、家族での過ごし方
- 雪遊び: 雪だるま作り、そり遊び、初めての雪体験
- 節分: 豆まき、恵方巻、家族の様子
- 温かい食べ物: 鍋料理、おでん、温かいココアなど
4. 特別な体験や感動したこと
心に残る特別な体験は、感情豊かな作文になります。
初めての体験
- 初めての一人お留守番: 不安だったこと、工夫したこと
- 初めての宿泊学習: 友だちと過ごした夜、お風呂の思い出
- 初めての料理: 作り方、失敗したこと、家族の反応
- 初めての電車一人旅: 行った場所、気をつけたこと
困難を乗り越えた体験
- 苦手なことに挑戦: 跳び箱が跳べるようになった、泳げるようになった
- ケガや病気: 入院の体験、周りの人の優しさ
- 怖かったけど頑張ったこと: 注射、高いところ、暗いところなど
感動した出来事
- 誕生日のサプライズ: 家族や友だちからのプレゼント
- 生き物との出会い: 野生動物を見た、虫を観察した、ペットの成長
- 美しい自然: 星空、虹、夕日、雪景色などの感動
5. 作文が書きやすくなるヒント
題材選びで悩んだときに役立つヒントをご紹介します。
作文カレンダーを作る
月ごとに起きた出来事をカレンダーに簡単にメモしておくと、振り返りやすくなります。
写真を見る
家族旅行や学校行事の写真を見ると、当時の記憶が蘇りやすくなります。
「できごとノート」を作る
小さなことでも、毎日の出来事や気づいたことをメモしておくと、題材が豊富になります。
家族や友だちと話す
「最近楽しかったことは?」など、会話の中から題材のヒントが見つかることも。
「好きなもの・こと」リストを作る
自分の好きなものや興味あることをリストにしておくと、書きたいことが見つかりやすくなります。
どの題材を選ぶにしても、自分が「書きたい!」と思えるものを選ぶのが一番です。小さな体験や気づきも、あなたにとっては大切な宝物。自分の言葉で素直に表現してみましょう。
お子さんが作文を書くときの親のサポート方法
お子さんが作文を書くときの親のサポート方法
作文は、お子さんの思考力や表現力を育てる大切な学習です。親としてどのようにサポートすれば、お子さんが楽しく作文を書けるようになるでしょうか。具体的な方法をご紹介します。
1. 話を聞いてメモしてあげる
聞き方のコツ
- オープンな質問を心がける: 「今日は何があった?」ではなく「今日の遠足で一番楽しかったことは?」など具体的に聞く
- 相づちを打ちながら聞く: 「へえ!」「それから?」「そうなんだね」など、興味を持って聞く
- 話の腰を折らない: 急かさず、最後まで聞く姿勢を見せる
メモの取り方
- キーワードだけをサッと書く: 「海」「貝殻」「大きな波」など、お子さんの話のポイントをメモ
- 時系列に沿って整理: 「朝→バス→海→昼食→帰り」など流れがわかるように
- 感情を表す言葉も書き留める: 「嬉しかった」「怖かった」「悲しかった」など
実践例
「遠足の作文を書きたいんだけど、何を書けばいいかな?」と悩むお子さんに 「遠足で何があったか教えてくれる?私がメモするね」と声をかけ、話を聞きながらキーワードをメモ。 「これを見て、どれから書きたい?」と順番を一緒に考える。
2. 質問をして考えを引き出す
効果的な質問例
- 五感を刺激する質問:
- 「そこではどんな音が聞こえた?」
- 「その食べ物はどんな味だった?」
- 「触ってみてどんな感じだった?」
- 気持ちを引き出す質問:
- 「そのとき、どんな気持ちだった?」
- 「なぜそう思ったの?」
- 「一番印象に残ったのはどんなところ?」
- 比較や例えを促す質問:
- 「それは何かに似ていた?」
- 「もし動物に例えるなら、どんな動物みたいだった?」
会話の例
お子さん:「動物園に行きました。ゾウを見ました。」 親:「ゾウはどんな風だった?大きさはどれくらい?」 お子さん:「すごく大きくて、車みたいだった!」 親:「へえ!近くで見るとどう感じた?」 お子さん:「ちょっと怖かったけど、鼻が長くて面白かった」
3. 一緒に作文の構成を考える
構成表の作り方
- 大きな紙を用意して三つに区切る: 上から「はじめ」「なか」「おわり」
- 付箋を使って整理: お子さんの話を付箋に書いて、適切な場所に貼っていく
- 矢印で順序を示す: 「なか」の部分は特に、時間の流れがわかるように矢印をつける
カード方式
- 小さなカードを用意: 出来事や感想を一つずつカードに書く
- 床やテーブルに並べる: カードを動かしながら順番を考える
- 一度並べたら読み上げる: 流れを確認し、必要に応じて並べ替える
マインドマップの活用
- 真ん中に題材を書く: 例えば「運動会」と中央に書く
- 枝を広げる: 「リレー」「応援」「お弁当」など関連することを書く
- さらに枝を広げる: 「リレー」から「バトン渡し」「転んだ」「追い抜いた」など
4. 書いた作文を読んで褒める
効果的な褒め方
- 具体的に褒める: 「よく書けたね」ではなく「この『ドキドキした』という表現がいいね」など
- 成長を認める: 「前よりも順序がわかりやすくなったね」など進歩を指摘する
- 努力を褒める: 「難しい漢字も調べて書いたんだね」など過程も認める
NG例と良い例
NG例:「まあまあ書けてるけど、誤字が多いね」 良い例:「こんなに詳しく書けているね!特にこの部分が面白いよ。誤字も一緒に見てみよう」
フィードバックのバランス
- 良いところ3つ:改善点1つくらいの割合を意識する
- まずは内容を褒めてから、誤字脱字などは後から一緒に直す
5. 書きやすい環境づくり
物理的な環境
- 静かで集中できる場所を用意: テレビやゲームから離れた場所
- 文房具を揃える: お気に入りのノート、鉛筆、消しゴムなど
- 辞書や資料を手元に: 漢字辞典、図鑑など参考になるものを用意
心理的な環境
- 時間的余裕を持つ: 「早く書きなさい」と急かさない
- リラックスした雰囲気を作る: 「失敗してもいいよ」という安心感を与える
- お茶やお菓子を用意: 適度な休憩も大切
6. 作文のアイデアを広げる工夫
絵日記からスタート
- まず出来事を絵で描いてもらう
- 絵を見ながら「これは何をしているところ?」と質問する
- 絵に吹き出しをつけて、会話や気持ちを書き込む
写真を活用する
- 家族旅行や学校行事の写真を見せる
- 「この時どう思った?」「これは何をしているところ?」と質問する
- 写真を時系列に並べて、ストーリーを考える
音声メモの活用
- お子さんの話を録音する(許可を得てから)
- 一緒に聞き直して「これは面白いね」「ここは詳しく書くといいね」とアドバイス
- 音声を文字に起こす作業を手伝う
7. 年齢に応じたサポート方法
小学3年生の特徴
- 自分の考えや感情を表現できるようになる時期
- 語彙が増え、文章がつながりを持ち始める
- まだ書くことに時間がかかることも
具体的なサポート例
- 書き出しのパターンを教える: 「○月○日、〜へ行きました」など定型文から始める
- 「です・ます」の統一を意識させる: 敬体と常体の混在に気づかせる
- 接続詞の使い方を教える: 「そして」「しかし」「なぜなら」などの使い方
8. 継続するための工夫
作文ノートの作成
- お気に入りのノートを「作文ノート」として用意する
- 日付と題名をつけて保存していく
- 定期的に読み返して成長を感じられるようにする
家族で回し読み
- 書いた作文を家族で読む時間を作る
- 「○○さんの作文を読んでください」と作者になったつもりで読む
- 感想を伝え合う
作文コンクールへの応募
- 地域や全国の作文コンクールに挑戦してみる
- 応募することそのものを褒める
- 結果よりもチャレンジしたことを評価する
9. 困った時の対処法
書き始められない時
- お話タイムから始める: まず話してから書くようにする
- **「私だったら〜と書くかな」**と例を示す(押し付けにならない程度に)
- 最初の一文だけ一緒に考える
集中力が続かない時
- 短い時間で区切る(15分書いたら5分休憩など)
- 「はじめ」だけ書いて休憩、次に「なか」と段階的に進める
- ご褒美システムを取り入れる(〇文字書いたらシールを貼るなど)
書くことがないと言う時
- 「一番〜なことは?」と具体的に聞く
- 「もし友達に話すとしたら何て言う?」と問いかける
- 身近な出来事を5つ挙げて、その中から選ばせる
お子さんの作文力を伸ばすには、日常的なコミュニケーションがとても大切です。「今日は何があった?」「どう思った?」と会話する習慣をつけることで、お子さんは自然と自分の考えや感情を言葉にできるようになります。焦らず、楽しみながらサポートしてあげてください。
作文が苦手なお子さんへのアドバイス
1. 作文ノートを作る
毎日短い文でも書く習慣をつけると、少しずつ書くことに慣れていきます。
2. 音読をする
本や教科書を音読すると、言葉のリズムや表現が身につきます。
3. 言葉集めをする
好きな言葉や新しく知った言葉をノートに書き留めておくと、作文を書くときに役立ちます。
4. 作文を書く前に話す
書く前に話すことで、伝えたいことが整理されます。
まとめ
小学3年生の作文は、「はじめ・なか・おわり」の構成を意識し、五感を使って具体的に書くことがポイントです。お子さんの体験や感じたことを大切にしながら、楽しく作文に取り組めるようサポートしてあげましょう。
作文は練習を重ねるほど上手になります。毎日の小さな出来事や感動を大切にして、少しずつ書く習慣をつけていくといいですね。お子さんの成長に合わせて、このガイドを参考にしながら、作文の楽しさを発見してください!
最後に、作文はお子さんの個性や考えを表現する大切な手段です。「正解」を求めるのではなく、自分らしい表現を見つける喜びを感じられるようにしましょう。
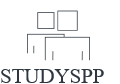
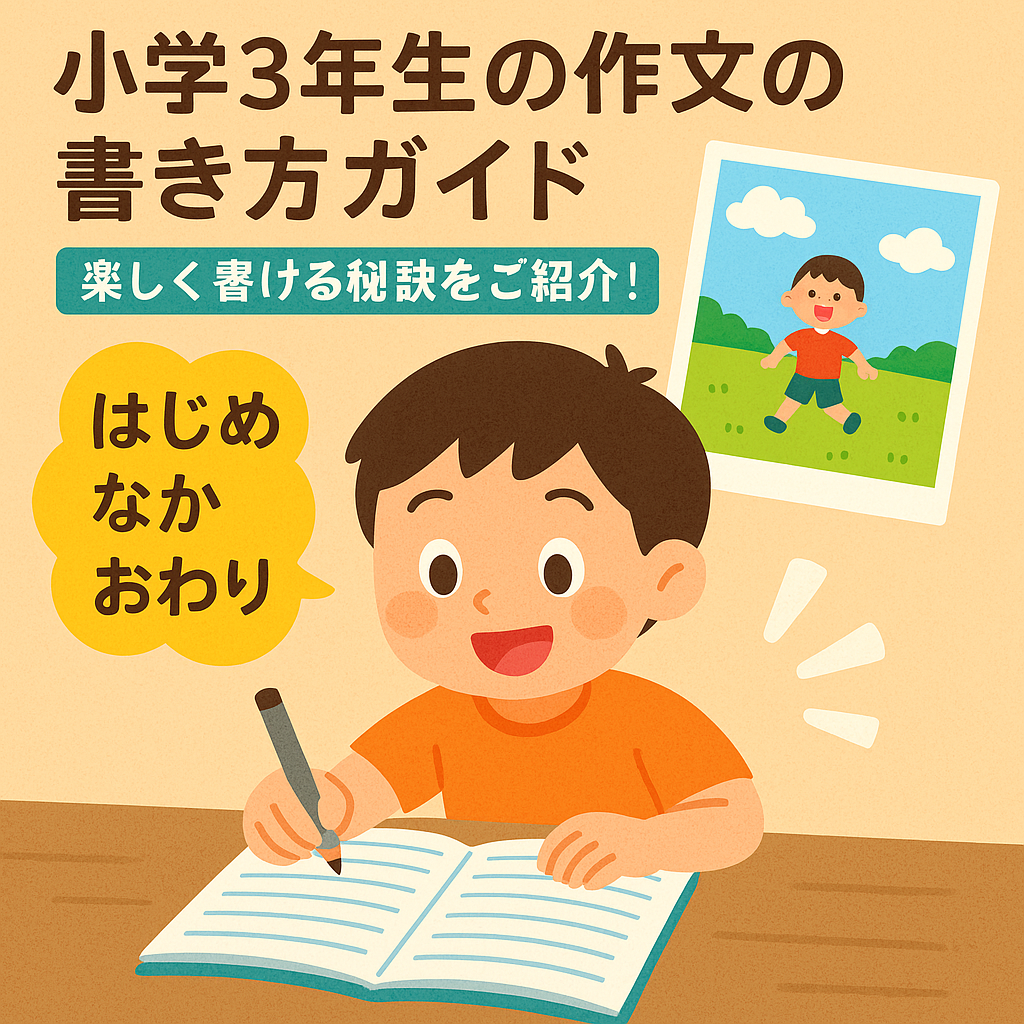
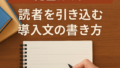

コメント