古文を学ぶ上で避けて通れないのが助動詞の習得です。多くの受験生や古文学習者が苦手とするこの分野ですが、適切な方法で学べば決して難しくありません。本記事では、古文の助動詞を効率的に覚えるための方法と、実際の古文作品に登場する具体例を豊富に紹介します。
1. 古文の助動詞を覚える重要性
古文において助動詞は、文の意味を大きく左右する重要な役割を持っています。例えば「見る」という動詞に「き」「けり」「つ」「ぬ」「たり」「り」などの助動詞が付くことで、時制や話者の心情などが表現されます。古文を正確に読み解くためには、助動詞の知識が不可欠なのです。
助動詞をマスターすることで得られるメリット:
- 古文の内容理解が格段に深まる
- 文法問題への対応力が向上する
- 古典作品特有の微妙なニュアンスを理解できる
- 古文の読解スピードが上がる
- 古文単語の覚え方はこちら
2. 助動詞の基本分類と覚え方
古文の助動詞は大きく分けて以下のように分類できます:
時制を表す助動詞
- 過去:き、けり、つ、ぬ、たり、り
- 例文:「昔、男ありけり」(昔、ある男がいたそうだ)
- 例文:「われ見き」(私は見た)
- 例文:「花散りぬ」(花が散ってしまった)
- 例文:「月出でたり」(月が出ている)
推量・意志を表す助動詞
- む、べし、らむ、けむ、まし
- 例文:「明日、参らむ」(明日、参りましょう)
- 例文:「急ぎ行くべし」(急いで行くべきだ)
- 例文:「いかならむ」(どのようであろうか)
- 例文:「何事ありけむ」(何事があったのだろうか)
- 例文:「見まほしかりけるものを見ましものを」(見たいと思っていたものを見たかったなあ)
打消を表す助動詞
- ず
- 例文:「知らず」(知らない)
- 例文:「言はざりき」(言わなかった)
受身・使役・可能を表す助動詞
- る・らる、す・さす
- 例文:「人に笑はる」(人に笑われる)
- 例文:「鳥を飛ばさす」(鳥を飛ばせる)
- 例文:「言ふべくもあらず」(言うこともできない)
敬意を表す助動詞
- る・らる、す・さす
- 例文:「君は御覧ず」(君はご覧になる)
- 例文:「姫君おはす」(姫君がいらっしゃる)
断定を表す助動詞
- なり、たり
- 例文:「これは花なり」(これは花である)
- 例文:「静かなる夜」(静かな夜)
- 例文:「優れたる技」(優れた技)
覚え方のコツ:機能別グループ化
助動詞を機能ごとにグループ化して覚えると効率的です。例えば、過去を表す助動詞「き」と「けり」は一緒に覚え、その違い(「き」は体験、「けり」は伝聞・気づき)も同時に理解しておくとよいでしょう。
「き」と「けり」の違いを示す例
- 「昨日、山に登りき」(自分が直接体験した過去)
- 「その山には昔、神社ありけり」(伝え聞いた過去)
「つ」と「ぬ」の違いを示す例
- 「手紙を書きつ」(自分の意志で書き終えた)
- 「花が散りぬ」(自然に散ってしまった)
覚え歌の例
「き・けり・つ・ぬ・たり・り」は「過去と完了を表すなり」と韻を踏んで覚える方法も効果的です。
3. 活用形別の助動詞の覚え方
助動詞は接続する活用形によっても分類できます。
未然形に接続する助動詞
- む、じ、ず、る・らる、す・さす など
- 例文:「明日、参らむ」(明日、参りましょう)
- 例文:「言はじ」(言うまい)
- 例文:「知らず」(知らない)
- 例文:「見らる」(見られる)
- 例文:「書かす」(書かせる)
連用形に接続する助動詞
- き、けり、つ、ぬ、たり、り など
- 例文:「花咲きき」(花が咲いた)
- 例文:「月出でけり」(月が出たことだ)
- 例文:「道行きつ」(道を行き終えた)
- 例文:「雪降りぬ」(雪が降ってしまった)
- 例文:「舟浮きたり」(舟が浮いている)
- 例文:「霧立ちり」(霧が立ちこめている)
終止形に接続する助動詞
- なり(断定)、らし など
- 例文:「これは梅の花なり」(これは梅の花である)
- 例文:「雨降るらし」(雨が降るようだ)
連体形に接続する助動詞
- ごとし など
- 例文:「雪の降るごとし」(雪が降るようだ)
- 例文:「花の散るがごとし」(花が散るようだ)
已然形に接続する助動詞
- ば(已然形+ば=仮定条件)
- 例文:「雨降らば、行かじ」(雨が降れば、行くまい)
- 例文:「月出でば、帰らむ」(月が出たら、帰ろう)
覚え方のコツ:語呂合わせ
例えば、未然形に接続する助動詞は「むずさる」(む、ず、さす、る)と語呂合わせで覚えるなど、工夫すると記憶に定着しやすくなります。
活用形による接続の覚え歌
- 「未然形は むずさる(む・ず・さす・らる)」
- 「連用形は きけつぬたり(き・けり・つ・ぬ・たり・り)」
- 「終止形は ならし(なり・らし)」
- 「連体形は ごとし」
- 「已然形は ば」
活用形と助動詞の組み合わせ例
- 「行か(未然形)+む」→「行かむ」(行こう)
- 「見(未然形)+ず」→「見ず」(見ない)
- 「咲き(連用形)+ぬ」→「咲きぬ」(咲いてしまった)
- 「思ふ(終止形)+なり」→「思ふなり」(思うのである)
- 「照る(連体形)+ごとし」→「照るごとし」(照るようだ)
- 「思へ(已然形)+ば」→「思へば」(思えば)
4. 意味による分類と覚え方
意味のグループごとに助動詞を整理して覚えるのも効果的です。以下、主要な意味分類と具体的な例文を交えて説明します。
過去・完了の助動詞
「き」:過去の事実(体験)
- 意味:話者が直接体験した過去の事実を表します
- 活用:連用形に接続
- 例文:「わが心、うれしくありき」(私の心は嬉しかった)
- 例文:「昨日、都に行きき」(昨日、都へ行った)
- 使い分けのポイント:自分が実際に見たり感じたりした経験を表現する時に使います
「けり」:過去の事実(伝聞・気づき)
- 意味:①他人から聞いた過去の事実、②自分が気づいた事実を表します
- 活用:連用形に接続
- 例文(伝聞):「むかし、男ありけり」(昔、男がいたそうだ)
- 例文(気づき):「花散りけり」(あ、花が散っていたのだな)
- 使い分けのポイント:「き」と違い、直接体験していない事柄や、後から気づいた事実に使います
「つ」:完了(主体的)
- 意味:主体の意志で動作が完了したことを表します
- 活用:連用形に接続
- 例文:「手紙を書きつ」(手紙を書き終えた)
- 例文:「荷物を運びつ」(荷物を運び終えた)
- 使い分けのポイント:自分の意志で行った行為が完了した場合に使います
「ぬ」:完了(自然発生的)
- 意味:自然に物事が完了したことを表します
- 活用:連用形に接続
- 例文:「花が散りぬ」(花が散ってしまった)
- 例文:「日が暮れぬ」(日が暮れてしまった)
- 使い分けのポイント:自然現象や意志に関係なく起こる変化に使います
「たり」:完了・存続
- 意味:動作が完了し、その状態が続いていることを表します
- 活用:連用形に接続
- 例文:「門に車立てたり」(門に車が置いてある)
- 例文:「雪積もりたり」(雪が積もっている)
- 使い分けのポイント:完了した状態が現在も続いていることを強調します
「り」:存続
- 意味:ある状態が続いていることを表します
- 活用:連用形に接続
- 例文:「霧立ちり」(霧が立ちこめている)
- 例文:「物思ひり」(物思いにふけっている)
- 使い分けのポイント:「たり」よりも存続の意味が強く、完了のニュアンスは薄いです
推量・意志の助動詞
「む」:推量・意志・勧誘
- 意味:①これからの推量、②話者の意志、③勧誘を表します
- 活用:未然形に接続
- 例文(推量):「雨降らむ」(雨が降るだろう)
- 例文(意志):「明日行かむ」(明日行こう)
- 例文(勧誘):「共に遊ばむ」(一緒に遊ぼう)
- 使い分けのポイント:文脈によって意味が変わるため、前後の文から判断します
「べし」:推量・必然・当然・可能
- 意味:①推量、②必然・義務、③可能性を表します
- 活用:連体形に接続
- 例文(推量):「彼は来るべし」(彼は来るだろう)
- 例文(必然):「急ぐべし」(急ぐべきだ)
- 例文(可能):「見るべき景色」(見ることができる景色)
- 使い分けのポイント:「可能性が高い」というニュアンスで使われることが多いです
「らむ」:現在の推量
- 意味:現在の状態についての推量を表します
- 活用:連体形に接続
- 例文:「何処にあらむ」(どこにあるのだろうか)
- 例文:「いかなる人ならむ」(どんな人なのだろうか)
- 使い分けのポイント:現在のことについて「〜だろうか」と推量する時に使います
「けむ」:過去の推量
- 意味:過去の状態についての推量を表します
- 活用:連体形に接続
- 例文:「何事ありけむ」(何事があったのだろうか)
- 例文:「誰が来たりけむ」(誰が来たのだろうか)
- 使い分けのポイント:過去のことについて「〜だったのだろうか」と推量する時に使います
「まし」:反実仮想
- 意味:実現しなかった願望や仮定を表します
- 活用:未然形に接続
- 例文:「会ひたまはましかば」(お会いできていたならば)
- 例文:「見ましものを」(見たかったなあ)
- 使い分けのポイント:「〜だったら良かったのに」というニュアンスで使います
覚え方のコツ
機能別のグループ化と例文の暗記
- 過去・完了グループ:「きけつぬたり」と唱えて覚える
- 暗記用例文:「花咲きき、月出でけり、手紙書きつ、雪降りぬ、門に車立てたり、霧立ちり」
- 推量・意志グループ:「むべらけま」と唱えて覚える
- 暗記用例文:「明日行かむ、急ぐべし、何処にあらむ、何事ありけむ、見ましものを」
意味の連想による記憶法
- 「き」→「聞き覚え」(直接体験した過去)
- 「けり」→「けれども聞いた」(伝聞の過去)
- 「つ」→「突き進んで完了」(主体的完了)
- 「ぬ」→「抜け落ちる」(自然に完了)
短文作成法
各助動詞を使った短い例文を自分で作成し、暗記します。例えば:
- 「春は来たりき」(春が来た – 体験)
- 「昔、神ありけり」(昔、神がいたそうだ – 伝聞)
- 「彼は去りぬ」(彼は去ってしまった – 自然発生的完了)
これらの方法を組み合わせることで、助動詞の意味を体系的に理解し、効率よく覚えることができます。特に、古文を読む際に実際に使われている助動詞を意識して確認することで、より定着が進みます。
5. 助動詞の接続パターンを覚える方法
助動詞がどの活用形に接続するかを理解することは非常に重要です。接続のパターンを効率的に覚えるための具体的な方法を紹介します。
接続パターンの例
未然形に接続する助動詞
- 未然形+む → 推量・意志
- 「行かむ」(行こう)
- 「見む」(見よう)
- 「聞かむ」(聞こう)
- 未然形+じ → 打消の意志
- 「言はじ」(言うまい)
- 「書かじ」(書くまい)
- 「見じ」(見まい)
- 未然形+ず → 打消
- 「行かず」(行かない)
- 「見ず」(見ない)
- 「聞かざりき」(聞かなかった)※「ず」の連用形「ざり」+「き」
連用形に接続する助動詞
- 連用形+き → 過去(体験)
- 「行きき」(行った)
- 「見き」(見た)
- 「聞きき」(聞いた)
- 連用形+つ → 完了(主体的)
- 「書きつ」(書き終えた)
- 「読みつ」(読み終えた)
- 「歩みつ」(歩み終えた)
- 連用形+ぬ → 完了(自然発生的)
- 「散りぬ」(散ってしまった)
- 「消えぬ」(消えてしまった)
- 「流れぬ」(流れてしまった)
終止形に接続する助動詞
- 終止形+なり → 断定
- 「美しなり」(美しいのだ)
- 「高しなり」(高いのだ)
- 「寒しなり」(寒いのだ)
- 終止形+らし → 推定
- 「雨降るらし」(雨が降るようだ)
- 「人来るらし」(人が来るようだ)
- 「風吹くらし」(風が吹くようだ)
連体形に接続する助動詞
- 連体形+ごとし → 比況
- 「雪の降るごとし」(雪が降るようだ)
- 「花の散るごとし」(花が散るようだ)
- 「雲の流るるごとし」(雲が流れるようだ)
已然形に接続する助動詞
- 已然形+ば → 仮定条件
- 「行けば」(行けば)
- 「見れば」(見れば)
- 「聞けば」(聞けば)
覚え方のコツ:カラフルなマーカー
活用表を作る際、接続するパターンごとに色分けすると記憶に残りやすくなります。例えば、過去・完了の助動詞は青色、推量は緑色というように色分けします。
色分けの例
- 未然形接続:赤色
- 連用形接続:青色
- 終止形接続:緑色
- 連体形接続:紫色
- 已然形接続:オレンジ色
語呂合わせで覚える接続パターン
各活用形に接続する助動詞を語呂合わせで覚えます。
- 未然形:「むずさるじ」(む、ず、さす、らる、じ)
- 連用形:「きけつぬたり」(き、けり、つ、ぬ、たり、り)
- 終止形:「なんらしくめり」(なり、らし、めり)
- 連体形:「ごとしなり」(ごとし、なり)
- 已然形:「ばかり」(ば)
動詞五段活用との組み合わせ練習
「書く」という動詞を例に、各活用形と助動詞の組み合わせを練習します。
- 未然形:「書か」
- 書か + む → 書かむ(書こう)
- 書か + ず → 書かず(書かない)
- 書か + る → 書かる(書かれる)
- 書か + す → 書かす(書かせる)
- 連用形:「書き」
- 書き + き → 書きき(書いた)
- 書き + けり → 書きけり(書いたそうだ)
- 書き + つ → 書きつ(書き終えた)
- 書き + ぬ → 書きぬ(書いてしまった)
- 書き + たり → 書きたり(書いている)
- 終止形:「書く」
- 書く + なり → 書くなり(書くのだ)
- 書く + らし → 書くらし(書くようだ)
- 連体形:「書く」
- 書く + ごとし → 書くごとし(書くようだ)
- 已然形:「書け」
- 書け + ば → 書けば(書けば)
接続パターンカード
助動詞と活用形の組み合わせをカードにして作成します。表面に助動詞、裏面に接続する活用形と例文を書いておき、繰り返し確認します。
カードの例
- 表:「む」
- 裏:「未然形に接続・推量・意志」「行かむ(行こう)」「見む(見よう)」
複合助動詞の接続パターン
助動詞が重なる場合の接続パターンも覚えておくと便利です。
- ず(未然形接続)+ らむ(連体形接続)→ ざらむ
- 例:「見ざらむ」(見ないだろう)
- き(連用形接続)+ けり(連用形接続)→ 使用不可(同じ機能の助動詞は重ねられない)
- ず(未然形接続)+ ば(已然形接続)→ ざれば
- 例:「行かざれば」(行かなければ)
実践練習:古文作品での確認
『伊勢物語』や『枕草子』などの古典作品から例文を抜き出し、助動詞の接続パターンを確認する練習も効果的です。
- 『伊勢物語』より:「昔、男ありけり」
- 「あり」の連用形「あり」+「けり」
- 『枕草子』より:「春はあけぼの。やうやう白くなりゆく山際」
- 「なりゆく」の「なり」は助動詞ではなく動詞の一部
これらの方法を組み合わせて繰り返し練習することで、助動詞の接続パターンを確実に習得できるでしょう。
6. 具体的な古文作品での助動詞の使用例
実際の古典作品から例文を挙げて解説します。
『徒然草』より
「花は盛りに、月は隈なきをのみ、見るものかは」 →「かは」は反語の助動詞「か」+係助詞「は」で、「見るものではない」という意味。
『枕草子』より
「春はあけぼの。やうやう白くなりゆく山際、少し明りて、紫だちたる雲の細くたなびきたる。」 →「たる」は完了の助動詞「たり」の連体形。「たなびきたる」で「たなびいている」の意。
『源氏物語』より
「光る君と人々言ひけり」 →「けり」は過去(伝聞)の助動詞。「光る君と人々が言っていたそうだ」の意。
『平家物語』より
「祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。沙羅双樹の花の色、盛者必衰の理をあらはす。」 →「あり」は存在の動詞、「あらはす」の「す」は使役の助動詞ではなく動詞の一部。
7. 助動詞の覚え方・練習方法いろいろ
古文の助動詞を効率的に覚えるためのさまざまな練習方法を詳しく説明します。
フラッシュカード法
基本的なカードの作り方
- 表面に助動詞とその接続形を書く(例:「き(連用形接続)」)
- 裏面に意味と例文を書く(例:「過去・体験、例:行きき(行った)」)
デジタルフラッシュカードの活用
- Anki、Quizlet、StudyStackなどのアプリを使って作成する
- 間隔反復学習機能を活用して効率的に記憶する
- 音声機能を使って例文を読み上げながら覚える
実践例
- 月曜日は「過去・完了」グループ(き、けり、つ、ぬ、たり、り)
- 火曜日は「推量・意志」グループ(む、べし、らむ、けむ、まし)
- 水曜日は「打消・受身・使役・可能」グループ(ず、る・らる、す・さす) というように、グループごとに曜日を決めて集中的に学習する
例文暗唱法
代表的な例文集の作成
各助動詞につき3つの例文を選び、その意味とともに暗唱します。
- 「き」の例文集:
- 「昨日、都に行きき」(昨日、都へ行った)
- 「花美しくありき」(花は美しかった)
- 「人多く集まりき」(人が多く集まった)
- 「けり」の例文集:
- 「昔、男ありけり」(昔、男がいたそうだ)
- 「雪降りけり」(雪が降ったことだ)
- 「月出でけり」(月が出たことだ)
古典作品からの例文採集
『源氏物語』『枕草子』『徒然草』など有名な古典作品から例文を集めて暗唱する方法も効果的です。
- 『枕草子』より:「春はあけぼの。やうやう白くなりゆく山際、少し明りて、紫だちたる雲の細くたなびきたる。」
- 「たる」は完了の助動詞「たり」の連体形
- 『徒然草』より:「花は散りぬべかりけり」
- 「ぬべかりけり」は完了の「ぬ」+推量の「べし」の連用形「べかり」+過去の「けり」
週間暗唱カレンダー
曜日ごとに異なる助動詞グループの例文を暗唱する計画を立てます。毎日5分間、声に出して読むだけでも効果があります。
助動詞変換トレーニング
基本動詞の活用変換表
「見る」「行く」「書く」など基本的な動詞を選び、さまざまな助動詞を付けて活用させる練習をします。
「見る」の助動詞変換表:
- 見 + き → 見き(見た)
- 見 + けり → 見けり(見たそうだ)
- 見 + つ → 見つ(見終えた)
- 見 + ぬ → 見ぬ(見てしまった)
- 見 + む → 見む(見よう)
- 見 + ず → 見ず(見ない)
- 見 + る → 見らる(見られる)
- 見 + させる → 見させる(見させる)
パターン練習
特定のパターンで練習します。例えば:
- 過去形パターン:「動詞+き」「動詞+けり」
- 完了形パターン:「動詞+つ」「動詞+ぬ」「動詞+たり」「動詞+り」
- 推量形パターン:「動詞+む」「動詞+べし」「動詞+らむ」「動詞+けむ」
意味変換練習
同じ動詞に異なる助動詞を付けて意味の違いを理解する練習です。
「散る」を例に:
- 散りき(散った – 私が見た)
- 散りけり(散ったそうだ/あ、散っていたのだな)
- 散りつ(散り終えた)
- 散りぬ(散ってしまった)
- 散りたり(散っている)
- 散らむ(散るだろう)
- 散るべし(散るはずだ)
- 散らざりき(散らなかった)
古文の音読
音読の手順
- 古文を声に出して読む
- 助動詞が出てきたら一旦止まる
- その助動詞の意味と接続形を確認する
- 文全体の意味を考える
- もう一度通して読む
助動詞マップの作成
意味関連マップ
助動詞を意味のつながりで図示します。中心に大きなカテゴリー(過去・完了、推量など)を置き、そこから枝分かれさせて関連する助動詞を配置します。
- 過去・完了グループ
- き(直接体験した過去)
- けり(伝聞・気づきの過去)
- つ(主体的完了)← 関連性 → ぬ(自然発生的完了)
- たり(完了・存続)← 関連性 → り(存続)
接続形マップ
活用形を中心に置き、そこから接続する助動詞を放射状に配置します。
- 未然形
- む(推量・意志)
- ず(打消)
- じ(打消の意志)
- る・らる(受身・可能・尊敬)
- す・さす(使役・尊敬)
- 連用形
- き(過去)
- けり(過去)
- つ(完了)
- ぬ(完了)
- たり(完了・存続)
- り(存続)
視覚的記憶法
マップに色やイラストを加えることで、視覚的記憶を強化します。例えば:
- 過去の助動詞は青色
- 完了の助動詞は緑色
- 推量の助動詞は黄色
- 打消の助動詞は赤色
助動詞カルタ作り
カルタの作り方
- 読み札:助動詞を使った短い文(例:「花散りぬ」)
- 取り札:意味と用法(例:「完了・自然発生的」)
遊び方
- 取り札を広げて並べる
- 読み手が読み札を読み上げる
- プレイヤーは該当する意味と用法の札を取る
応用バージョン
- 逆カルタ:意味から助動詞を当てる
- 接続カルタ:活用形から接続する助動詞を当てる
助動詞歌・語呂合わせの創作
助動詞の覚え歌
リズムに乗せて覚えやすくします。
- 過去・完了の助動詞の歌: 「き・けり・つ・ぬ・たり・り、過去と完了覚えましょう きは体験、けりは伝聞、つは主体的、ぬは自然に たりは完了の状態続く、りは単なる状態継続」
- 推量助動詞の歌: 「む・べし・らむ・けむ・まし、みんな推量助動詞 むは未来、べしは当然、らむは現在、けむは過去 まじは反実仮想、こうして覚えましょう」
オリジナル語呂合わせ
- 未然形接続:「むずかしさ(む、ず、か、さ)をる(る)」
- 連用形接続:「きっとけっこうつよいぬことたべり(き、け、つ、ぬ、た、り)」
- 終止形接続:「なるほどらしいめり(な、ら、め)」
古文問題集・過去問題での実践
解き方のコツ
- 問題文中の助動詞に印をつける
- その助動詞の接続形、意味を確認する
- 前後の文脈から使われ方を判断する
間違いやすい助動詞の組み合わせを重点的に練習
- 「き」と「けり」の区別
- 「つ」と「ぬ」の区別
- 「む」の多義性(推量・意志・勧誘)
復習ノートの作成
間違えた問題や理解が不十分だった助動詞を中心に復習ノートを作成します。
デジタルツールの活用
学習アプリの利用
- 「古文単語」「古文文法」などのアプリを活用
- 通学時間や寝る前の5分間など、隙間時間に練習
オンライン問題集
- 大学入学共通テストの過去問
- 各予備校のオンライン教材
SNSでの学習コミュニティ参加
- 学習仲間と一緒に助動詞クイズを出し合う
- 難しい用法について議論する
助動詞ゲームの作成
すごろくゲーム
マス目ごとに助動詞を配置し、そのマスに止まったら例文を言う
神経衰弱
助動詞カードとその意味カードをペアにして神経衰弱をする
クロスワードパズル
助動詞とその用法をヒントにしたクロスワードパズルを作成する
これらの方法を組み合わせて使うことで、古文の助動詞を楽しく効率的に覚えることができます。個人の学習スタイルに合わせて、最も効果的な方法を選んで実践してみましょう。
8. よくある間違いと対策
助動詞「き」と「けり」の混同
- 「き」:話者が直接体験した過去
- 「けり」:伝聞または気づきの過去
- 例文で比較:
- 「昨日、山に登りき」(自分が登った)
- 「昔、この地に城ありけり」(伝え聞いた)
「つ」と「ぬ」の使い分け
- 「つ」:主体的な完了
- 「ぬ」:自然発生的な完了
- 例文で比較:
- 「手紙を書きつ」(自分の意志で書き終えた)
- 「花が散りぬ」(自然に散ってしまった)
対策:対比表の活用
似ている助動詞を対比表にまとめ、違いを明確にしておくことが効果的です。
9. まとめ
古文の助動詞を効率よく覚えるためには、以下のポイントを意識しましょう:
- 機能別にグループ化して覚える
- 接続する活用形をパターン化する
- 実際の古典作品の例文と共に意味を理解する
- 繰り返し練習と復習を行う
- 助動詞同士の違いを明確に理解する
これらの方法を組み合わせれば、古文の助動詞は必ず習得できます。最初は大変かもしれませんが、少しずつ積み重ねていくことで、古文読解の大きな武器となるでしょう。
古文の助動詞をマスターすれば、古典の世界がより深く、より豊かに広がります。ぜひ本記事で紹介した方法を実践してみてください。
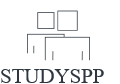
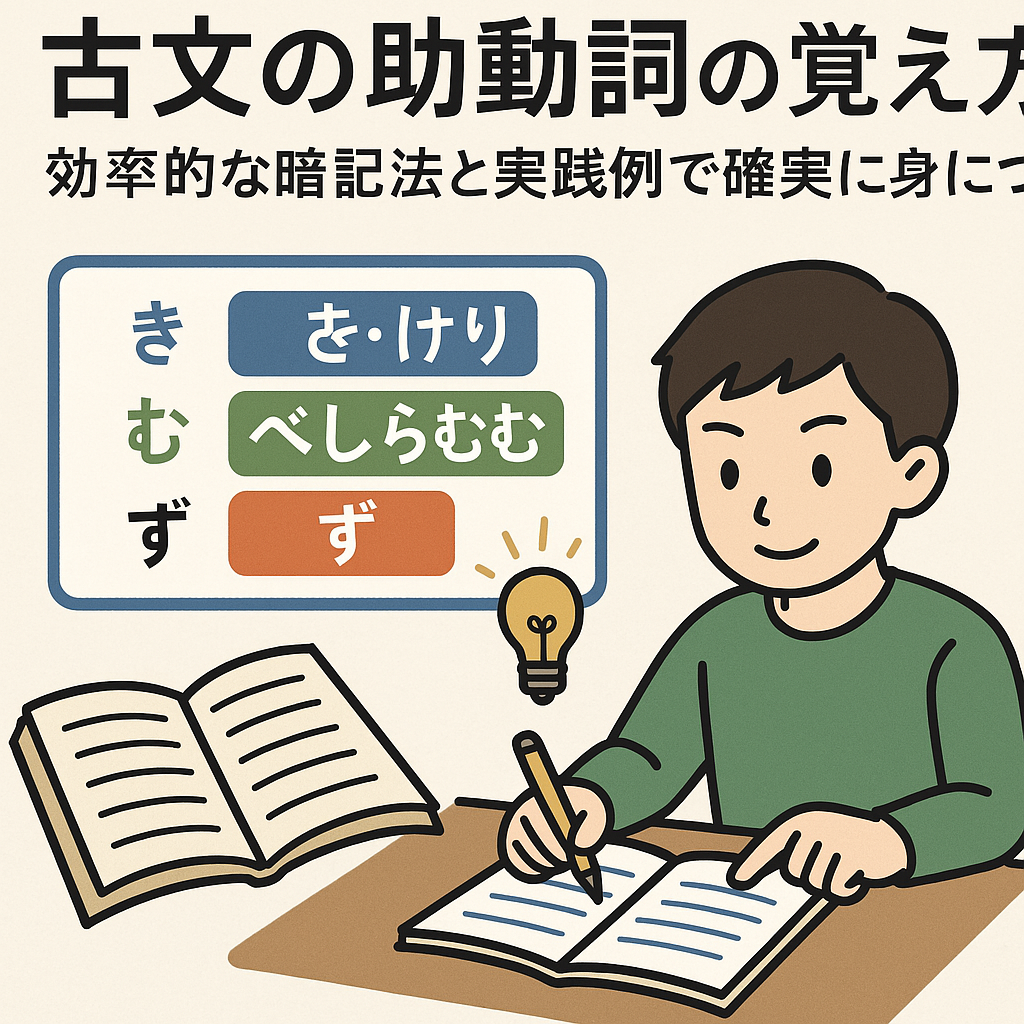


コメント