はじめに
中学生のみなさん、古文の勉強は難しいと感じていませんか?特に古文単語は現代語と似ているようで異なる意味を持つものが多く、覚えるのに苦労するかもしれません。しかし、適切な「連想記憶術」を使えば、古文単語の暗記はぐっと楽になります。この記事では、古文単語と現代語の共通点を見つけ出し、効率的に覚える方法をご紹介します。
連想記憶術とは?
連想記憶術とは、新しく覚えたい情報を、すでに知っている情報と関連付けて記憶する方法です。人間の脳は、バラバラの情報よりも「つながり」のある情報を覚えるのが得意です。古文単語を暗記する際も、現代語との共通点や語源、イメージなどと結びつけることで、記憶に定着しやすくなります。
古文単語と現代語の関係性
古文の言葉は、現代の日本語のルーツです。多くの古文単語は、形を変えながらも現代語に受け継がれています。例えば、「うつくし(美し)」という古語は、現代の「美しい」につながっていますが、古文では「かわいい」という意味でした。このような言葉の変遷を知ることで、古文単語の意味を理解しやすくなります。
品詞別・覚えやすい古文単語リスト
形容詞編
- あやし(怪し)
- 古文の意味:不思議だ、疑わしい
- 現代語との共通点:「怪しい」という言葉に残っている
- 連想のコツ:「あやしげな人影」を想像してみよう
- をかし(可笑し)
- 古文の意味:おもしろい、趣がある
- 現代語との共通点:「おかしい」(滑稽だ)という意味に変化
- 連想のコツ:「を」が「お」に変わっただけと考える
- いとほし(愛惜)
- 古文の意味:かわいそう、いたわしい
- 現代語との共通点:「いとおしい」(大切に思う)
- 連想のコツ:「いとほしい人」は「いたわりたい人」
- くやし(悔し)
- 古文の意味:残念だ、後悔する
- 現代語との共通点:「悔しい」という言葉で残っている
- 連想のコツ:意味がほとんど変わっていないので、現代語のイメージで覚える
- たのし(楽し)
- 古文の意味:楽しい、心地よい
- 現代語との共通点:「楽しい」という言葉に残っている
- 連想のコツ:意味がほぼ同じなので、現代語のイメージをそのまま活用
- うつくし(美し)
- 古文の意味:かわいい、愛らしい
- 現代語との共通点:「美しい」という言葉に変化
- 連想のコツ:古文では「小さく愛らしいもの」を指した→幼い子どもの愛らしさを想像
- かなし(悲し)
- 古文の意味:悲しい、つらい
- 現代語との共通点:「悲しい」という言葉でそのまま残っている
- 連想のコツ:意味がほぼ同じなので、現代語のイメージで覚える
- くるし(苦し)
- 古文の意味:つらい、苦しい
- 現代語との共通点:「苦しい」という言葉でそのまま残っている
- 連想のコツ:意味がほぼ同じなので、「くるしい思い」と覚える
- なつかし(懐かし)
- 古文の意味:親しみを感じる、好ましい
- 現代語との共通点:「懐かしい」という言葉に意味が変化
- 連想のコツ:古文では「親しみ」→現代では「思い出して親しみを感じる」
- めでたし(愛でたし)
- 古文の意味:すばらしい、立派だ
- 現代語との共通点:「めでたい」という言葉で残っている
- 連想のコツ:「目出度い」と漢字で書くと「目が出るほど良いこと」と覚えられる
- こころよし(快し)
- 古文の意味:気持ちが良い、快適だ
- 現代語との共通点:「快い」という言葉に残っている
- 連想のコツ:「心」が「良い」状態=気持ちがいい
- あはれなり(哀れなり)
- 古文の意味:風情がある、しみじみとした情趣を感じる
- 現代語との共通点:「哀れ」という言葉に意味が変化
- 連想のコツ:古文では「感動的な美しさ」→現代では「かわいそう」
- かしこし(賢し)
- 古文の意味:賢い、利口だ
- 現代語との共通点:「賢い」という言葉で残っている
- 連想のコツ:意味がほぼ同じなので、現代語のイメージで覚える
- けやけし(鮮やけし)
- 古文の意味:はっきりしている、明らかだ
- 現代語との共通点:「鮮やか」という言葉に関連
- 連想のコツ:「けやけしい色彩」=鮮やかな色を想像する
- くちをし(口惜し)
- 古文の意味:残念だ、悔しい
- 現代語との共通点:「口惜しい」という表現が残っている
- 連想のコツ:悔しくて「口」に出せない思い=「くちをしい」
- さびし(寂し)
- 古文の意味:わびしい、閑散としている
- 現代語との共通点:「寂しい」という言葉で残っている
- 連想のコツ:場所の寂しさから人の寂しさへと想像を広げる
- つよし(強し)
- 古文の意味:強い、力がある
- 現代語との共通点:「強い」という言葉で残っている
- 連想のコツ:意味がほぼ同じなので、「つよい力」と覚える
- にくし(憎し)
- 古文の意味:憎らしい、憎むべきだ
- 現代語との共通点:「憎い」という言葉で残っている
- 連想のコツ:現代語とほぼ同じだが、古文では「かわいくて憎らしい」という意味も
- はかなし(儚し)
- 古文の意味:頼りない、あてにならない、短命である
- 現代語との共通点:「儚い」という言葉で残っている
- 連想のコツ:「はかない夢」のように消えやすいイメージで覚える
- やさし(優し)
- 古文の意味:弱々しい、はかない
- 現代語との共通点:「優しい」という言葉に意味が変化
- 連想のコツ:古文では「弱くて守りたい」→現代では「思いやりがある」
- うれし(嬉し)
- 古文の意味:うれしい、喜ばしい
- 現代語との共通点:「嬉しい」という言葉で残っている
- 連想のコツ:意味がほぼ同じなので、現代語のイメージでOK
- おもし(重し)
- 古文の意味:重い、重々しい
- 現代語との共通点:「重い」という言葉に残っている
- 連想のコツ:「おも」は「面(顔)」も意味するので「顔が重い」=「深刻な表情」
- こひし(恋し)
- 古文の意味:恋しい、会いたい
- 現代語との共通点:「恋しい」という言葉で残っている
- 連想のコツ:「恋する」気持ちから「こひしい」と覚える
- たかし(高し)
- 古文の意味:高い、位が高い
- 現代語との共通点:「高い」という言葉で残っている
- 連想のコツ:意味がほぼ同じなので、「たかい山」と覚える
- ふかし(深し)
- 古文の意味:深い、奥深い
- 現代語との共通点:「深い」という言葉で残っている
- 連想のコツ:意味がほぼ同じなので、「ふかい森」と覚える
動詞編
- あはれぶ(哀れぶ)
- 古文の意味:同情する、かわいそうに思う
- 現代語との共通点:「哀れみ」という言葉に残っている
- 連想のコツ:「あはれな状況」を「あわれむ」と覚える
- 間違えやすい点:現代語では「哀れ」は「かわいそう」だが、古文では「風情ある」意味も
- いたはる(労る)
- 古文の意味:世話をする、大切にする
- 現代語との共通点:「労わる」「いたわる」という言葉で残っている
- 連想のコツ:「いた」は「痛」→痛みを和らげる=「いたわる」
- おぼゆ(覚ゆ)
- 古文の意味:思われる、感じられる
- 現代語との共通点:「覚える」という言葉に関連
- 連想のコツ:「~と思う」の受身形「~と思われる」と考える
- 間違えやすい点:現代語の「覚える」(記憶する)とは意味が異なる
- たばかる(謀る)
- 古文の意味:計画する、企てる
- 現代語との共通点:「謀る」という言葉に残っている
- 連想のコツ:「たばかり」と「謀略」を結びつける
- ながむ(眺む)
- 古文の意味:じっと見つめる、眺める
- 現代語との共通点:「眺める」という言葉で残っている
- 連想のコツ:意味がほぼ同じなので、「景色をながめる」イメージで覚える
- あく(飽く)
- 古文の意味:満足する、十分になる
- 現代語との共通点:「飽きる」という言葉に残っているが意味が変化
- 連想のコツ:「あくまで」(徹底的に)の語源
- 間違えやすい点:現代語の「飽きる」(興味を失う)とは反対の意味
- いふ(言ふ)
- 古文の意味:言う、話す
- 現代語との共通点:「言う」に変化
- 連想のコツ:「ふ」が「う」に変わると覚える
- おもふ(思ふ)
- 古文の意味:思う、考える
- 現代語との共通点:「思う」に変化
- 連想のコツ:「ふ」が「う」に変わると覚える
- かく(書く)
- 古文の意味:書く、描く
- 現代語との共通点:意味がほぼ同じ
- 連想のコツ:現代語と同じイメージで覚える
- きく(聞く)
- 古文の意味:聞く、尋ねる、効果がある
- 現代語との共通点:「聞く」「効く」として残っている
- 連想のコツ:「薬が効く」の「効く」も古文では「きく」
- 間違えやすい点:古文では「聞く」と「効く」が同じ「きく」
- しる(知る)
- 古文の意味:知る、わかる
- 現代語との共通点:意味がほぼ同じ
- 連想のコツ:現代語と同じイメージで覚える
- たつ(立つ)
- 古文の意味:立つ、出発する
- 現代語との共通点:「立つ」として残るが意味が狭まる
- 連想のコツ:「旅立つ」という言葉に古い意味が残っている
- 間違えやすい点:古文では「出発する」意味も強い
- とる(取る)
- 古文の意味:取る、捕まえる
- 現代語との共通点:意味がほぼ同じ
- 連想のコツ:現代語と同じイメージで覚える
- なく(泣く/鳴く)
- 古文の意味:泣く、鳴く
- 現代語との共通点:「泣く」「鳴く」として区別されるようになった
- 連想のコツ:古文では人の泣くことも動物の鳴くことも同じ「なく」
- 間違えやすい点:古文では漢字による区別がない
- まつ(待つ)
- 古文の意味:待つ、期待する
- 現代語との共通点:「待つ」として残っている
- 連想のコツ:「待ち望む」の意味を含む
- わたる(渡る)
- 古文の意味:渡る、及ぶ、広がる
- 現代語との共通点:「渡る」として残るが意味が狭まる
- 連想のコツ:「広く渡る」イメージで覚える
- 間違えやすい点:古文では範囲が広がることも意味した
- あはす(合はす)
- 古文の意味:合わせる、一致させる
- 現代語との共通点:「合わせる」に変化
- 連想のコツ:「あ」+「はす」→「あはす」→「あわせる」
- 間違えやすい点:「はす」が「わせる」に変化
- うつ(打つ)
- 古文の意味:打つ、叩く、~する(補助動詞)
- 現代語との共通点:「打つ」として残るが補助動詞の用法は少ない
- 連想のコツ:「~うつ」という形で「~し始める」の意味になることも
- 間違えやすい点:古文では補助動詞として幅広く使われた
- かへる(帰る/返る)
- 古文の意味:帰る、戻る、返る
- 現代語との共通点:「帰る」「返る」として区別されるようになった
- 連想のコツ:「もとの場所・状態に戻る」というイメージでまとめて覚える
- 間違えやすい点:古文では漢字による区別があいまい
- こふ(恋ふ)
- 古文の意味:恋い慕う、望む
- 現代語との共通点:「恋う」→「恋する」に変化
- 連想のコツ:「こがれる」(恋い焦がれる)と関連づける
- 間違えやすい点:古文では恋愛感情だけでなく、広く「慕う」意味も
- さく(咲く/裂く)
- 古文の意味:咲く、割れる、裂ける
- 現代語との共通点:「咲く」「裂く」として区別されるようになった
- 連想のコツ:花が開くイメージと、物が割れるイメージの共通点を考える
- 間違えやすい点:古文では同じ「さく」で表現
- しく(敷く)
- 古文の意味:敷く、広げる、並べる
- 現代語との共通点:「敷く」として残るが用法が狭まる
- 連想のコツ:「言い訳を敷く」など、現代でも比喩的に使う
- 間違えやすい点:古文では比喩的用法が多い
- なる(成る)
- 古文の意味:成る、~になる、鳴る、実がなる
- 現代語との共通点:「成る」「鳴る」「生る」として区別されるようになった
- 連想のコツ:変化全般を表す「なる」と覚える
- 間違えやすい点:古文では漢字による区別があいまい
- へだつ(隔つ)
- 古文の意味:離れる、距離がある
- 現代語との共通点:「隔たる」として残っている
- 連想のコツ:「へ」は「辺」→辺が遠い=「隔たる」
- 間違えやすい点:現代語ではあまり使わないが「隔たり」という名詞は残る
- みる(見る)
- 古文の意味:見る、確かめる、世話をする
- 現代語との共通点:「見る」として残るが意味が狭まる
- 連想のコツ:「子を見る」(世話をする)、「様子を見る」(確かめる)
- 間違えやすい点:古文では「世話をする」意味が強い場合もある
- ゆく/いく(行く)
- 古文の意味:行く、進む、時間が過ぎる
- 現代語との共通点:「行く」として残っている
- 連想のコツ:古文では「ゆく」が一般的、現代語では「いく」が一般的
- 間違えやすい点:「時が行く(過ぎる)」という用法も
- わく(湧く/沸く)
- 古文の意味:湧く、沸く、わき起こる
- 現代語との共通点:「湧く」「沸く」として残っている
- 連想のコツ:水が湧き出るイメージと感情が湧くイメージを結びつける
- 間違えやすい点:古文では感情表現にも多用
- あふ(合ふ/会ふ)
- 古文の意味:会う、合う、一致する
- 現代語との共通点:「会う」「合う」に変化
- 連想のコツ:「あふ」→「あう」と変化
- 間違えやすい点:古文では「会う」「合う」の区別があいまい
- いたる(至る)
- 古文の意味:到着する、達する、及ぶ
- 現代語との共通点:「至る」として残っているが硬い表現に
- 連想のコツ:「至る所」(いたるところ)の表現に残っている
- 間違えやすい点:現代では「至る」という言葉自体があまり使われない
- おふ(負ふ)
- 古文の意味:背負う、担う、持つ
- 現代語との共通点:「負う」に変化
- 連想のコツ:「おふ」→「おう」と変化、責任を「負う」
- 間違えやすい点:現代語では抽象的な意味で使うことが多い
- かなふ(叶ふ)
- 古文の意味:適う、できる、願いが実現する
- 現代語との共通点:「叶う」に変化
- 連想のコツ:「願いが叶う」の表現に残っている
- 間違えやすい点:現代語では主に「願望が実現する」意味で使う
- たてまつる(奉る)
- 古文の意味:差し上げる、捧げる(謙譲語)
- 現代語との共通点:「奉る」として残るが特殊な場面でのみ使用
- 連想のコツ:「捧げ物を立てて差し上げる」イメージ
- 間違えやすい点:現代語ではほとんど使われない敬語表現
- まうす(申す)
- 古文の意味:言う(謙譲語)
- 現代語との共通点:「申す」として残っている
- 連想のコツ:「申し上げる」の「申」
- 間違えやすい点:現代語では「申し訳ない」など限られた表現で使用
- はべり(侍り)
- 古文の意味:いる、ある(謙譲語・丁寧語)
- 現代語との共通点:現代語にはほぼ残っていない
- 連想のコツ:「侍」(さむらい)が「はべる」(仕える)からの連想
- 間違えやすい点:現代語にない表現なので注意
- たまふ(給ふ)
- 古文の意味:くださる(尊敬語)、あげる(謙譲語)
- 現代語との共通点:「~てくださる」の意味として「賜う」が残る
- 連想のコツ:目上の人が「与える」または「行う」こと
- 間違えやすい点:尊敬語と謙譲語両方の用法があり紛らわしい
- こころみる(試みる)
- 古文の意味:試す、やってみる
- 現代語との共通点:「試みる」として残っている
- 連想のコツ:「心」で「見る」→確かめる→試す
- 間違えやすい点:現代語では硬い表現になっている
- あらはす(表す/現す)
- 古文の意味:表す、現す、表現する
- 現代語との共通点:「表す」「現す」「著す」に分化
- 連想のコツ:「あら」は「新」→新しく見せる=「表す」
- 間違えやすい点:古文では表記による意味の区別があいまい
- ものす(物す)
- 古文の意味:書く、記す
- 現代語との共通点:ほとんど使われなくなった
- 連想のコツ:「もの」を「する」→物事を記録する
- 間違えやすい点:現代語ではまったく使われない
- まどふ(惑ふ)
- 古文の意味:迷う、惑わされる
- 現代語との共通点:「惑う」に変化したが使用頻度は低い
- 連想のコツ:「まどろむ」(うとうとする)との混同に注意
- 間違えやすい点:現代語では「惑わす」という他動詞形が多い
- ののしる(罵る)
- 古文の意味:大声で叫ぶ、騒ぐ、のろう
- 現代語との共通点:「罵る」(ののしる)として残るが意味が狭まる
- 連想のコツ:古文では「大声を出す」が原義、現代では「悪口を言う」
- 間違えやすい点:現代語では「悪口を言う」意味に限定
名詞編
- おもかげ(面影)
- 古文の意味:人の顔や姿の印象
- 現代語との共通点:「面影」という言葉でそのまま残っている
- 連想のコツ:「おも(顔)」の「かげ(影)」と分解して覚える
- こころばへ(心映え)
- 古文の意味:心の持ちよう、性格
- 現代語との共通点:「心映え」という言葉は古風な表現として残っている
- 連想のコツ:「心」が「映える」様子を想像する
- たより(便り)
- 古文の意味:手紙、消息
- 現代語との共通点:「便り」という言葉でそのまま残っている
- 連想のコツ:「た」は「手」→手紙=「たより」
- みやび(雅び)
- 古文の意味:上品さ、優美さ
- 現代語との共通点:「雅び」「雅」という言葉で残っている
- 連想のコツ:「宮廷」の「美」→「みやび」
- よすが(縁)
- 古文の意味:つながり、きっかけ
- 現代語との共通点:現代ではあまり使われないが、「縁」の意味で理解できる
- 連想のコツ:「よ」は世+「すが」は「すがる」→世にすがるもの=「縁」
- あだ(徒)
- 古文の意味:はかない、無駄な、軽薄な
- 現代語との共通点:「徒事(あだごと)」「徒(あだ)になる」などの表現に残る
- 連想のコツ:「徒労」の「徒」=無駄
- 間違えやすい点:現代では「仇」という漢字もあてられるが意味は異なる
- あやめ(菖蒲/文目)
- 古文の意味:菖蒲の花、模様の区別
- 現代語との共通点:「菖蒲」として植物名に残る
- 連想のコツ:「あや」は模様→模様のある花=「あやめ」
- 間違えやすい点:「文目」と書くと模様の意味、「菖蒲」と書くと植物の意味
- いのち(命)
- 古文の意味:命、寿命、運命
- 現代語との共通点:「命」として残っている
- 連想のコツ:意味はほぼ同じだが、古文では運命的な意味合いが強い
- 間違えやすい点:古文では「運命」「定め」のニュアンスも含む
- いろ(色)
- 古文の意味:色、色彩、恋愛、美しさ
- 現代語との共通点:「色」として残るが意味が狭まる
- 連想のコツ:「色恋」「色めく」など複合語に古い意味が残る
- 間違えやすい点:古文では「恋愛」「情事」の意味で使われることが多い
- うし(憂し)
- 古文の意味:つらい、悲しい、不幸な
- 現代語との共通点:「憂い」「憂鬱」などの言葉に残る
- 連想のコツ:「牛」ではなく「憂」の字から連想する
- 間違えやすい点:現代語の「牛(うし)」と同音異義語
- おく(奥)
- 古文の意味:内側、奥、心の内
- 現代語との共通点:「奥」として残っている
- 連想のコツ:空間的な「奥」と心理的な「奥」をイメージする
- 間違えやすい点:古文では抽象的・心理的な意味でもよく使われた
- おほかた(大方)
- 古文の意味:たいてい、おおよそ、たぶん
- 現代語との共通点:「大方」として残っている
- 連想のコツ:「大きい」+「方向」→全体的に見て
- 間違えやすい点:現代語では「大部分」の意味が強いが、古文では推量の意味も
- かぎり(限り)
- 古文の意味:限度、最大限、限られた時間
- 現代語との共通点:「限り」として残っている
- 連想のコツ:「かぎる」(限る)の名詞形
- 間違えやすい点:「命限り」など、古文特有の表現もある
- かげ(影/陰)
- 古文の意味:影、光、恩恵、本質
- 現代語との共通点:「影」「陰」として残るが意味が狭まる
- 連想のコツ:「日陰」も「日影」も古くは同じ「ひかげ」
- 間違えやすい点:現代語の「影」より広い意味を持つ
- かたち(形)
- 古文の意味:形、姿、容姿、美しさ
- 現代語との共通点:「形」として残るが意味が狭まる
- 連想のコツ:「かたちよし」で「容姿が美しい」
- 間違えやすい点:古文では「美しい容姿」の意味が強い
- ここち(心地)
- 古文の意味:気分、感じ、心持ち
- 現代語との共通点:「心地よい」などの表現に残る
- 連想のコツ:「心」の「地」(基盤)→心の基本状態
- 間違えやすい点:現代語では単独で使うことが少なく、複合語で残る
- さが(性)
- 古文の意味:生まれつきの性質、本性
- 現代語との共通点:「気性」「性格」の「性」
- 連想のコツ:「さ」は接頭語、「が」は「我」→自分の本質
- 間違えやすい点:現代語ではほとんど使われないが、「性格」の意味
- さま(様)
- 古文の意味:様子、状態、身分、敬称
- 現代語との共通点:「様子」や敬称「様」として残る
- 連想のコツ:「~のさま」で「~の様子」
- 間違えやすい点:古文では敬称以外の用法が多い
- すがた(姿)
- 古文の意味:姿、見た目、様子
- 現代語との共通点:「姿」として残っている
- 連想のコツ:「すがたかたち」(姿形)のように使われることも
- 間違えやすい点:意味はほぼ同じだが、古文では「心の姿」も表す
- そら(空)
- 古文の意味:空、うわべ、偽り
- 現代語との共通点:「空」として残るが意味が狭まる
- 連想のコツ:「空々しい」(うわべだけの)表現に古い意味が残る
- 間違えやすい点:古文では「偽り」「うわべ」の意味でもよく使われた
- たけ(丈)
- 古文の意味:背の高さ、長さ、程度
- 現代語との共通点:「丈」として残るが使用頻度は低い
- 連想のコツ:「背丈」「力の及ぶ丈」などの表現に残る
- 間違えやすい点:現代語では主に複合語の形で残る
- つま(妻/夫)
- 古文の意味:配偶者(夫・妻どちらも)、恋人
- 現代語との共通点:「妻」として女性配偶者の意味で残る
- 連想のコツ:男女どちらの配偶者も「つま」と呼んだ
- 間違えやすい点:現代語では女性配偶者のみを指す
- ながめ(眺め/長雨)
- 古文の意味:眺め、眺望、長雨
- 現代語との共通点:「眺め」「長雨」として残るが別の言葉に
- 連想のコツ:「眺める」行為と結果が「ながめ」
- 間違えやすい点:「ながめ」一語で「眺め」と「長雨」の両方の意味
- なさけ(情け)
- 古文の意味:思いやり、愛情、恋心
- 現代語との共通点:「情け」として残るが意味が狭まる
- 連想のコツ:「情けは人の為ならず」の「情け」
- 間違えやすい点:古文では「恋愛感情」の意味もある
- なごり(名残)
- 古文の意味:別れの悲しみ、痕跡、余韻
- 現代語との共通点:「名残」として残っている
- 連想のコツ:「名」の「残り」→思い出に残る名
- 間違えやすい点:現代語では「痕跡」「余韻」の意味が強い
- はらから(同胞)
- 古文の意味:兄弟姉妹、同胞
- 現代語との共通点:「同胞」の意味で文語的表現として残る
- 連想のコツ:「腹」から生まれた者→兄弟姉妹
- 間違えやすい点:現代語では詩的・文語的表現としてのみ使用
- ふみ(文/書)
- 古文の意味:手紙、文章、書物
- 現代語との共通点:「文」として残るが意味が変化
- 連想のコツ:「踏む」ではなく「文字を書いたもの」
- 間違えやすい点:現代語では「手紙」の意味ではあまり使わない
- まごころ(真心)
- 古文の意味:偽りのない心、誠実な気持ち
- 現代語との共通点:「真心」として残っている
- 連想のコツ:「真」の「心」→偽りのない心
- 間違えやすい点:意味はほぼ同じだが、古文でも重要な概念だった
- みやこ(都)
- 古文の意味:都、京都、首都
- 現代語との共通点:「都」として残るが、特に京都を指すことが多い
- 連想のコツ:「みや」(宮)のある「ところ」→「みやこ」
- 間違えやすい点:古文では特に「京都」を指すことが多い
- むかし(昔)
- 古文の意味:過去、以前、大昔
- 現代語との共通点:「昔」として残っている
- 連想のコツ:「昔々あるところに」の「むかし」
- 間違えやすい点:古文では時間的な距離感が現代と異なる場合がある
- もの(者/物)
- 古文の意味:物、者、こと、理由
- 現代語との共通点:「物」「者」として残るが用法が狭まる
- 連想のコツ:「ものがなし」(物悲しい)など、感情表現にも使われる
- 間違えやすい点:古文では抽象的な概念も表し、非常に幅広く使われた
- もののあはれ(物の哀れ)
- 古文の意味:もの(対象)への深い感動、風情
- 現代語との共通点:「物の哀れ」として文学用語に残る
- 連想のコツ:「もの」(対象)への「あはれ」(感動)
- 間違えやすい点:現代語の「哀れ」(かわいそう)とは異なる美意識
- やど(宿)
- 古文の意味:宿、家、住まい
- 現代語との共通点:「宿」として残るが意味が狭まる
- 連想のコツ:「宿泊所」だけでなく「住まい」全般を指した
- 間違えやすい点:現代語では主に「宿泊施設」の意味
- やま(山)
- 古文の意味:山、山岳、最高潮
- 現代語との共通点:「山」として残るが比喩的用法が少ない
- 連想のコツ:「山場」「山を張る」など比喩表現に古い用法が残る
- 間違えやすい点:古文では比喩的な用法が多い
- ゆかり(縁)
- 古文の意味:関係、由来、縁故
- 現代語との共通点:「縁」「所縁」の意味で残る
- 連想のコツ:「行き来り」→関係がある
- 間違えやすい点:現代語では「血縁関係」の意味合いが強い
- ゆめ(夢)
- 古文の意味:夢、幻、決して~ない(否定の強調)
- 現代語との共通点:「夢」として残るが否定の強調用法は少ない
- 連想のコツ:「ゆめゆめ」で「決して~するな」の意味も
- 間違えやすい点:古文では否定を強調する副詞としても使われた
- よ(世)
- 古文の意味:世の中、時代、人生
- 現代語との共通点:「世」として残っている
- 連想のコツ:「世を忍ぶ」「世を逃れる」などの表現に残る
- 間違えやすい点:古文では「人生」「時代」の意味でも多用
- よそおい(装い)
- 古文の意味:身なり、服装、化粧
- 現代語との共通点:「装い」として残っている
- 連想のコツ:「装う」(よそおう)の名詞形
- 間違えやすい点:古文では特に女性の化粧・服装を指すことが多い
- わざ(業/技)
- 古文の意味:仕事、技術、行為、わざと
- 現代語との共通点:「業」「技」「技術」として残る
- 連想のコツ:「わざとらしい」の「わざ」は「行為」
- 間違えやすい点:古文では「わざと」(故意に)という副詞的用法もある
- をりふし(折節)
- 古文の意味:時、時節、折々
- 現代語との共通点:「折節」という言葉は残るが使用頻度は低い
- 連想のコツ:「をり」(折・時)+「ふし」(節・時期)
- 間違えやすい点:現代語ではほとんど使われない
イメージで覚える古文単語
単語の意味を絵や状況で想像すると、記憶に残りやすくなります。例えば:
- あやし(怪し):暗い路地裏で不審な人影がちらついているシーン
- をかし(可笑し):面白い出来事に微笑んでいる平安時代の貴族
- いとほし(愛惜):怪我をした小動物を優しく撫でている場面
- うつくし(美し):かわいい子どもの笑顔
このように、単語の意味にあった具体的なイメージを思い浮かべながら覚えると効果的です。
古文単語カードの作り方
古文単語を効率よく覚えるためのカードの作り方を紹介します:
- 表面に古文単語と読み方を書く
- 裏面に以下の情報を書く
- 意味
- 現代語との共通点
- 連想イメージ
- 使用例(簡単な文)
例:
- 表面:「あやし(怪し)」
- 裏面:
- 意味:不思議だ、疑わしい
- 現代語:「怪しい」として残っている
- 連想:暗い路地裏の不審な人影
- 例文:「あやしき人あり」(不審な人がいる)
カードは電車の中や休み時間など、ちょっとした時間に繰り返し見ることで記憶に定着します。
テスト前の効率的な復習法
- グループ分けによる復習:似た意味の古文単語をグループ化して覚える
- 例:感情を表す言葉(うれし、かなし、くやし)など
- 対義語でセットにする:意味が反対の言葉をペアで覚える
- 例:「たのし(楽し)」と「くるし(苦し)」
- 文脈で覚える:単語だけでなく、短い文章の中で使い方を覚える
- 例:「花のいろいと(とても)うつくし(かわいらしい)」
- 音読して覚える:声に出して読むことで、耳からも情報を入れる
- 反復学習のタイミング:
- 覚えた直後
- 1日後
- 3日後
- 1週間後
- テスト前日
この間隔で復習すると、記憶の定着率が高まります。
まとめ
古文単語を覚えるのに最も効果的な方法は、現代語との共通点を見つけ、イメージを結びつける「連想記憶術」です。単に暗記するのではなく、意味のつながりを理解することで、長期的な記憶につながります。
この記事で紹介した方法を実践して、古文単語を楽しく効率的に覚えましょう。古文の世界が広がると、日本文化や言葉の奥深さを発見できるはずです。
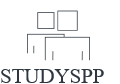
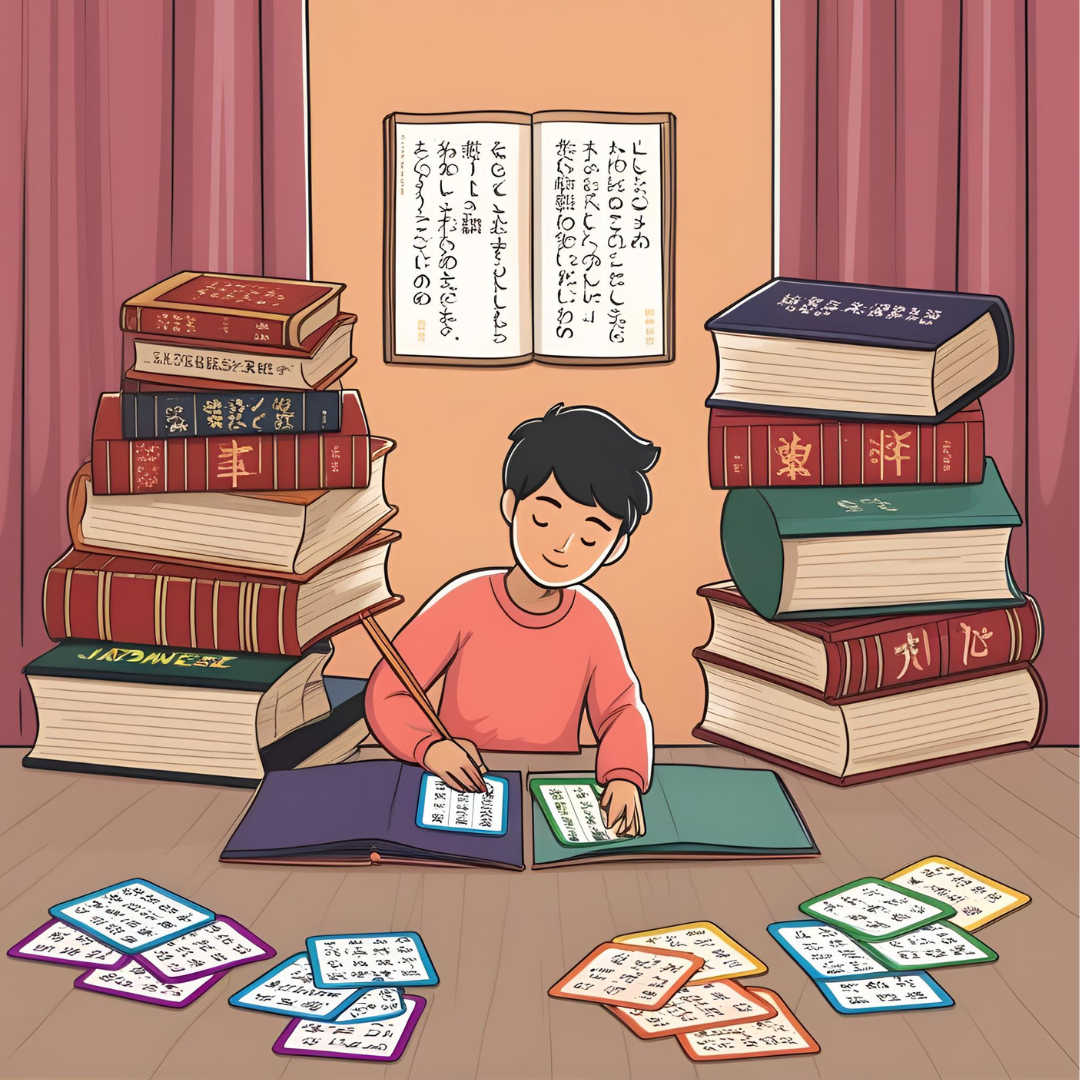


コメント